古代に興味を抱く者にとって、考古学者の研究の進展に学ぶ点が多いのは、いまさら論を要しまい。
武蔵国高麗郡は無住の地であったので、日高市史によると、次の史実を知る。
「716年(霊亀2年)(今から1300年前)に、関東各地(当時の7カ国)に住んでいた「高麗人」1,799人が武蔵国に集められ、「高麗郡」ができました。
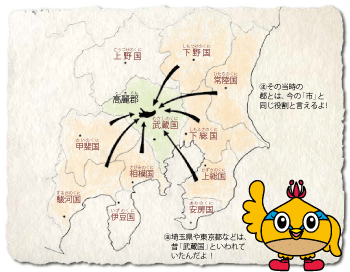
「高麗郡」ができたことは、昔の歴史書である『続日本紀(しょくにほんき)』に書かれています。
高麗人たちの渡来人は、大陸の進んだ技術や文化を伝えました。」
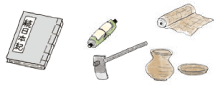
もう少し補充説明をすれば、「駿河・甲斐・相模・上総・下総・常陸・下野の七ヶ国に居住していた1,799人の高麗人〔高句麗(こうくり)系渡来人及びその子孫〕達が、現在の日高・飯能市域を中心に設置された高麗郡に移動した(移動させられた)」と考えられる。天智5年(666)から持統4年(690)にかけて渡来した朝鮮半島出身の高句麗人の一部が東国7か国にいったんは定着したものの、そこからさらに武蔵国高麗郡に移り来たと説く。
此の翌年、つまり養老元年(717)には朝鮮半島からの渡来人(百済人・高句麗人)に対して、『続日本紀』養老元年11月条に
「 甲辰,高麗、百濟二國士卒,遭本國亂,投於聖化。朝庭憐其絕域,給復終身。」
とあり、終身課役を免除する特権に恵まれたので、高麗郡に集合した約1800人の高句麗人に朗報となっただろう。
人が移動すれば、文化や親族組織、居住形態、さらには生業・物質文化・宗教生活.など多様な文化要素が移動する。
考古学的発掘成果が各地から積みあがると、慧眼の考古学者によって鋭い着眼に驚かされる。
「高麗人の移住を証明する資料が、飯能市内の遺跡発掘調査で発見されています。堂ノ根(どうのね)遺跡1号住居跡出土資料です(飯能市指定文化財 写真)。須恵器〔すえき 窯を使い高温で焼成(しょうせい)した灰色・硬質の土器〕の坏〔つき 飲食物を盛った椀形の器(うつわ)〕と蓋には、金雲母(きんうんも)や白色の長石(ちょうせき)が含まれ、常陸国(ひたちのくに 現在の茨城県)の窯で焼かれた須恵器と考えられています。また、土師器(はじき 野焼きした赤褐色・軟質の土器)の甕(かめ)は、その形と整形方法から「常総型(じょうそうがた)」と呼ばれる下総国(しもうさのくに ほぼ現在の千葉県北部)から常陸国南部に流通していたものとわかります。これらの土器の年代は7世紀末から8世紀前葉で、建郡の頃におおむね一致するため、常陸国南部あたりに住んでいた高麗人が、移住時に持ってきた可能性が考えられています。」
「土器は出土状態から、1号住居跡の住人が使用したものと推測されます。1号住居跡は一辺約7メートルの竪穴で当時としてはかなり大きいことと、割れやすい土師器の甕を含め、まとまった数の土器を持参していることなどから、1号住居跡に住んだ高麗人は、比較的富裕な層であったと推定されています。(村上)」
注釈:堂ノ根遺跡( 埼玉県飯能市大字芦刈場字後野375-1 )
堂ノ根遺跡1号住居跡出土遺物 (市指定)/飯能市-Hanno City-
当然と言えば当然であるが、歴史的文献の説明の裏付けを求める考古学者が出現してもおかしくない、だからといって誰にもできる仕事ではなく、日々の考古学的発掘作業と並行して、少なくとも7か国の発掘報告書類に目を配り、連想と想像を重ねる地味な研鑽が求められる。
まず、この記述に注目されるのは、食糧難で住居もなく「追放された、行く当てもない流浪の民、高句麗人」が辿り着いたのではなく、「比較的富裕層」の高句麗人たちも中央政府の命令の下で移動させられた事実である。
次に、この七か国の人々は高麗郡に移り住んだのち、バラバラに散在したか、それとも集団で居住したかである。望蜀の感もあるが、高麗郡府から見て、どのような配置された各居住地であったのかも気になるところである。
それにしても不思議なのは、約1800人に達する高句麗人が、たとえ関東平野の空閑地であったとしても、高麗郡に集合させたか、である。これを語る資料はない。いつものように、古代において記述するまでもなく、誰もの周知の事実であったからである。時を経た我々を悩ますのは、当時の常識や通念を持ち合わせないゆえに、文献資料の骨片から推測をするしかない。
次のように。高麗郡出身者でもっとも著名人は、旧姓「背奈」の高倉福信であることに誰しも異論を唱えないだろう。「背奈」姓といえば、彼のサクセスストリーは別としても、彼が天平宝字元年(757)に、藤原仲麻呂と共に造東大寺司に対して緑青616斤8両を上納した事実である(『『大日本古文書』4-223頁)。
背奈氏が高麗郡に近接する秩父の銅山から産出する緑青をまとまって入手できることから推測して、直接に銅山経営に手を染めていたか、それともその技術を所有していたか、さらには豊かな財力を以て購入できたかなどを仮定できる。
エビデンスもないままのまったくのあてずっぽうであるが、背奈氏は朝鮮半島から持参した緑青製造技術を保持していたか、あるいはその技術者を配下に於いていたことは確実である。 ところで、それを平城京に大量に運搬した時に、何に活用したかを問わなくてはならない。
私の仮説は次の通りである。例えば平城京が「青丹によし奈良の都」とよばれたように、日中韓の寺刹は「丹青」も塗布していた。日中韓における丹青顔料「緑青」は、蓮の葉のように濃い緑色を帯び「荷葉」と呼んだ。その緑青製造法を熟知していたのが、朝鮮半島からの渡来人であった背奈氏であったと思われる。
当時の平城京では、大規模な仏教寺院や仏教美術品に大量な緑青の需要があった。各地から進上されたにせよ、背奈氏の関与を特記し、しかも時の権力者藤原仲麻呂と併記している点に、その記述の裏面にある政治的な思惑を想像させる。
なお、秩父鉱業所のHPによると、「緑青」を作る孔雀石は、
https://trekgeo.net/m/s/chrysocollaCHICHIBU.htm
次のような4鉱山↓での採掘地を知る。
幅30mm。結晶質石灰岩中に見られる塊状の珪孔雀石。 薄青塊状の部分が珪孔雀石。周囲の薄茶色の部分は褐鉄鉱で汚染された大理石。 左上のやや錆びた金色の部分は黄銅鉱で、珪孔雀石はこれから導かれた。
I型(磁鉄鉱系列)の石英閃緑岩の接触変成によるスカルンと複合した中低温熱水鉱床の天水酸化帯より。
この産地の珪孔雀石は、1929年(昭和4年)に初めて記載された。
幅30mm。結晶質石灰岩中に見られる塊状の珪孔雀石。 薄青塊状の部分が珪孔雀石。周囲の薄茶色の部分は褐鉄鉱で汚染された大理石。 左上のやや錆びた金色の部分は黄銅鉱で、珪孔雀石はこれから導かれた。
I型(磁鉄鉱系列)の石英閃緑岩の接触変成によるスカルンと複合した中低温熱水鉱床の天水酸化帯より。
この産地の珪孔雀石は、1929年(昭和4年)に初めて記載された。
別産地の例
参考文献
飯能市遺跡調査会『堂ノ根遺跡第1次調査』(飯能市遺跡調査会 1993年)
飯能市教育委員会『掘り起こせ!地中からのメッセージ』(飯能市教育委員会 2010年)
富元久美子「渡来人による新郡開発 ―武蔵国高麗郡―」『古代の開発と地域の力』(高志書院 2014年)
富元久美子「高麗郡建都と東金子窯」211-228頁
【平成28年8月号】高麗人(こまひと)移住を物語る土器たち/飯能市-Hanno City-
なお、下記の報告によると、
堂ノ根遺跡1号住居跡出土遺物 (市指定)/飯能市-Hanno City-
「指定された出土遺物は、破片も含めて総点数208点(うち常陸産80点)から成っています。内訳は、以下の通りです。
これらは当地域の古代史を解明する上で不可欠であり、とても重要な資料です。

0 件のコメント:
コメントを投稿